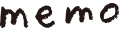うちの子はまだ4才でまだまだ先の話だけれど、先輩お母さんの話を聞いたり色々な記事を読んでいるうちに、9才ごろにあるらしい子供の変化が気になってきました。
この頃に親を客観視し出してある種の親離れがあるようで、シュタイナー教育に基づいた講座を開いている先生は「9才の危機」と表現していました。
↓このブログもシュタイナー系。
「9才の危機」森へ行こう(心とからだと子育てと)
「9才の危機(その2)」森へ行こう(心とからだと子育てと)
ここを読むと幼い頃に自然や大人との関わりなど、現実社会の中に楽しさを知れている事がこの時期に対しての準備になるとのことです。
自分はどうだったかなぁと考えてしまいます・・。
でも、何の人の手も加わってないものとか、現実的な日々の作業とか人との関わりに楽しさ(日々に喜び)を感じる力が身に付けられていたらとてもいいだろうなぁ、身につけたいなぁと今現在強く思ってはいるのは確か。
そして、このプレゼンも思い出しました。
ベンジャミン・ザンダー「音楽と情熱」TED
これを見てとても感動しのたのですがそれは今はおいておいて、、
ここではクラシック音楽の素晴らしさをプレゼンされています。
子供のピアノの上達の仕方を7才のリズムの取り方は〜という感じで、11才まで説明があって、そこで上手く楽しさが見つけられないと、ピアノを続けられないと言っています。
7才はリズムを一音一音とっていて、11才は楽譜全部でひとつのリズムで捉えて、曲に込められた思いを理解して強弱がつけられるようになるようです。
ですが、うまく理解できないでリズムを細かく単調にとっているだけでは、疲れやすく飽きてしまって続かないとのことで、とても印象に残りました。私自身も習字とかそろばんとかを早いうちから習っていたのに行かなくなってしまったのは、これくらいの時期だった気がします・・
9才ごろにきちんと何かに向き合って、楽しさを見出す経験をして熱中出来るかどうかが大事そうだなぁと思いました。こういう変化があると知っていれば、子供への接し方を比較的考えやすくなりそうですよね。
私はとっくに9才の何倍も生きてしまっていますが、リズムのとり方=意識の仕方と考えて、もう少し疲れない生き方をしたいものだと考えたりしていました 笑。社会活動が怖かったり自信が無かったり、何かに熱中して自分でやり続けていることは無い気がします・・。そして本当にやりたいはずの作品づくりからは逃避しがち。自分の問題としてもこの件に興味がわきました。
子育てしていると、こんな風に自分を育て直しているような気持ちにもなります。
と言いつつ、これまで緊張と緩和とか、ハレとケについて知った時に、同じようにヒントを得られたと思って考えてみてもなかなか上手くやれていなかったりします・・きっと自分でもがくしかないのでしょうね(助けて〜)