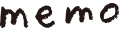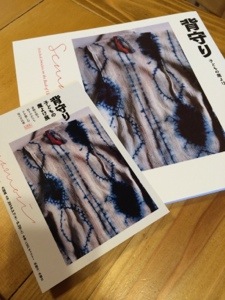考えること
植物写真家・埴沙萌さんの本や映像などをみていると、植物の美しさと、そのしくみにとても感心する。子孫を残すために、独自のやり方で種を自分で飛ばしたりするものがいたり、それを風や虫たちに託すものがいたり。よく考えてそのしくみを編み出したんだなぁ、という感じがして愛おしくもなってくる。
植物はただ、そこにいるだけのように思えるのに。
気温や光や、何かしらの条件がそろうと芽を出し、すくすく育って、やがて種を土へ落とし、枯れていくのを繰り返す、その決まった流れの中に、よくできたしくみがつまっている。考えていないようで、よく観察すると考えてそうしているようにみえてくる。
それも「考える」ということにあてはまるのなら、私のいつもやっているつもりの「考える」ってなんなのだろう?別にしなくてもいいことをしているのかな?
脳みそのない植物が、あんなに精巧に出来ていて、美しくもあるんだから。頭の中をぐるぐるさせずに行動するだけでよかったりするのかもしれない。と思った。
ふと思い出した。
森に詳しい方のお話会での質疑応答で「なんで間伐作業をする必要があるのでしょうか?」というのに対しこんな風にこたえていた。
「自然に放っておいても間伐を行うのと同じようないい状況になるんだけれど、それには100年くらいかかってしまう。だから人間が手を加えるんです。」
人間には脳みそがあって、効率よく目の前の状況を良い方向に変えていけるんだな、「こういう状況が好ましい・そのためにはこうするのがいい」という知恵を道具のように使っているのかもしれないなぁと思った。植物のしくみにも知恵のようなものを感じるけれど、進化して生き残ってきた形がそうみえるだけなのかもしれない。
植物が何代にもわたって進化して生き残るけれど、人間は1人でも、植物より多くの知恵も持てるんだ。何のための知恵なのか、知恵をどう使うのがいいのかとか、自分なりに考えてみたくなった。生きるため、楽しむため、よい社会にするため・・・?
あれ?考える話が、知恵の話になってしまった。